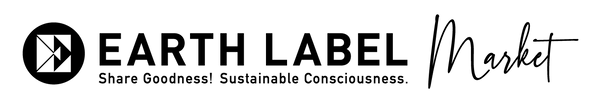MAGAZINE

🌿バリ島発・心と体を癒す伝統飲料「ジャムウティー」
🌺 バリの癒しをお家で 朝日が昇るころ、バリ島の人々は小さな花びらのお供えを神様に捧げ、「今日もありがとう」と静かに祈りを捧げます。緑が生い茂るウブドの棚田では、霧の中でお香の香りがふわりと漂い、ケチャダンスの太鼓のリズムが遠くから聞こえてくる――。 そんな“心と自然がつながる島”バリには、昔から人々の暮らしに寄り添う**ハーブティー「ジャムウ」**の文化があります。 🪶 バリに昔から伝わる“植物のくすり” ジャムウの歴史はとても古くて、1000年以上も前にさかのぼります。王族の美容や健康のために作られたのが始まりで、今では地元の人たちの日常のセルフケアとして親しまれています。 素材はすべて自然由来。ウコン(ターメリック)やショウガ、レモングラスなど、身近なハーブやスパイスがたっぷり使われているんです。 飲むと、体がじんわり温まったり、気持ちがスッと軽くなったり。「体の中から整う感じ」が、まさにバリの知恵なんですね🌿 ☕ 今どきのジャムウは“モダン&おしゃれ”に進化中 最近のバリ島では、スパやヨガリトリートでジャムウティーを出すお店が増えています。カフェでは見た目も可愛い「モダンジャムウ」が登場していて、ナチュラル志向の人たちに大人気。 「デトックスしたい」「リラックスしたい」など、目的に合わせて選べるのも楽しいポイントです。 🌿 ジャムウティーの主なタイプ せっかくなので、代表的な3タイプをご紹介します👇 Infusion(インフュージョン):ミントやレモングラスなど爽やかな香り。日中のリフレッシュにぴったり。 Detox(デトックス):ターメリックやジンジャーがベース。体の巡りをサポートしてくれるブレンド。 Relax(リラックス):カモミールやラベンダーなどのやさしい香りで、夜のひと息におすすめ。 その日の気分や体調で選べるのが魅力です🌙 🍃 EARTH LABEL MARKETのジャムウティーで、気軽にバリ時間を そんなジャムウティーをおうちで楽しめるのが、EARTH LABEL MARKETで販売中のこちらの3種類です👇 💧 ナディスハーバルハーブティ(Infusion) すっきりとした味わいで、朝の目覚めや午後のリフレッシュに。 🌼...
🌿バリ島発・心と体を癒す伝統飲料「ジャムウティー」
🌺 バリの癒しをお家で 朝日が昇るころ、バリ島の人々は小さな花びらのお供えを神様に捧げ、「今日もありがとう」と静かに祈りを捧げます。緑が生い茂るウブドの棚田では、霧の中でお香の香りがふわりと漂い、ケチャダンスの太鼓のリズムが遠くから聞こえてくる――。 そんな“心と自然がつながる島”バリには、昔から人々の暮らしに寄り添う**ハーブティー「ジャムウ」**の文化があります。 🪶 バリに昔から伝わる“植物のくすり” ジャムウの歴史はとても古くて、1000年以上も前にさかのぼります。王族の美容や健康のために作られたのが始まりで、今では地元の人たちの日常のセルフケアとして親しまれています。 素材はすべて自然由来。ウコン(ターメリック)やショウガ、レモングラスなど、身近なハーブやスパイスがたっぷり使われているんです。 飲むと、体がじんわり温まったり、気持ちがスッと軽くなったり。「体の中から整う感じ」が、まさにバリの知恵なんですね🌿 ☕ 今どきのジャムウは“モダン&おしゃれ”に進化中 最近のバリ島では、スパやヨガリトリートでジャムウティーを出すお店が増えています。カフェでは見た目も可愛い「モダンジャムウ」が登場していて、ナチュラル志向の人たちに大人気。 「デトックスしたい」「リラックスしたい」など、目的に合わせて選べるのも楽しいポイントです。 🌿 ジャムウティーの主なタイプ せっかくなので、代表的な3タイプをご紹介します👇 Infusion(インフュージョン):ミントやレモングラスなど爽やかな香り。日中のリフレッシュにぴったり。 Detox(デトックス):ターメリックやジンジャーがベース。体の巡りをサポートしてくれるブレンド。 Relax(リラックス):カモミールやラベンダーなどのやさしい香りで、夜のひと息におすすめ。 その日の気分や体調で選べるのが魅力です🌙 🍃 EARTH LABEL MARKETのジャムウティーで、気軽にバリ時間を そんなジャムウティーをおうちで楽しめるのが、EARTH LABEL MARKETで販売中のこちらの3種類です👇 💧 ナディスハーバルハーブティ(Infusion) すっきりとした味わいで、朝の目覚めや午後のリフレッシュに。 🌼...

健康茶でストレスフリーな毎日を
今年の夏も暑くて、いつまで暑さが続くやらなんて思っていましたら、急に底冷えする寒さがやってきましたね。温かい飲み物やお鍋が恋しい季節の到来です🍂私のように寒暖差アレルギーなどに悩まされる方もいらっしゃるでしょうか。活動的だった気候から一転して、原因不明の頭痛やめまいなどが起こりやすいですよね。自律神経とか気圧とか、対処が難しくてなんだかモヤモヤして1日を終える・・・そんなことにならないように、今回はストレスを軽減する対処法をご提案いたします。 現代社会では、仕事や人間関係、家庭環境、体調不良、情報の多さなど、日常の中にたくさんのストレスが潜んでいます。 「リラックスしたいけど、時間がない」「カフェインを控えて、心を落ち着かせたい」そんな方におすすめなのが、健康茶によるストレスフリー習慣です。 自然の恵みをいただくお茶時間は、心と体をやさしく整えてくれます。 ① 現代人のストレス事情 ・毎日忙しくてリラックスできない・睡眠の質が落ちている・心と体の不調が増えている → そんなときに「手軽にできる癒し習慣」として健康茶が注目されています。 ② 健康茶がストレスに効く理由 ・香りや温かさがリラックス効果を高める(嗅覚と自律神経の関係)・ハーブや成分が心身を整える(カフェインレス・抗酸化など)・”飲む瞑想”のような時間(マインドフルな習慣)③ ストレスケアにおすすめの健康茶5選 お茶の種類 効果 飲むタイミング ポイント カモミールティー 安眠・リラックス 就寝前 はちみつを加えると◎ レモンバームティー 不安を和らげる 午後〜夜 すっきりした香りで気分転換 ジャスミン茶 緊張緩和・集中力アップ 午前〜午後 勉強や仕事中にもおすすめ ルイボスティー...
健康茶でストレスフリーな毎日を
今年の夏も暑くて、いつまで暑さが続くやらなんて思っていましたら、急に底冷えする寒さがやってきましたね。温かい飲み物やお鍋が恋しい季節の到来です🍂私のように寒暖差アレルギーなどに悩まされる方もいらっしゃるでしょうか。活動的だった気候から一転して、原因不明の頭痛やめまいなどが起こりやすいですよね。自律神経とか気圧とか、対処が難しくてなんだかモヤモヤして1日を終える・・・そんなことにならないように、今回はストレスを軽減する対処法をご提案いたします。 現代社会では、仕事や人間関係、家庭環境、体調不良、情報の多さなど、日常の中にたくさんのストレスが潜んでいます。 「リラックスしたいけど、時間がない」「カフェインを控えて、心を落ち着かせたい」そんな方におすすめなのが、健康茶によるストレスフリー習慣です。 自然の恵みをいただくお茶時間は、心と体をやさしく整えてくれます。 ① 現代人のストレス事情 ・毎日忙しくてリラックスできない・睡眠の質が落ちている・心と体の不調が増えている → そんなときに「手軽にできる癒し習慣」として健康茶が注目されています。 ② 健康茶がストレスに効く理由 ・香りや温かさがリラックス効果を高める(嗅覚と自律神経の関係)・ハーブや成分が心身を整える(カフェインレス・抗酸化など)・”飲む瞑想”のような時間(マインドフルな習慣)③ ストレスケアにおすすめの健康茶5選 お茶の種類 効果 飲むタイミング ポイント カモミールティー 安眠・リラックス 就寝前 はちみつを加えると◎ レモンバームティー 不安を和らげる 午後〜夜 すっきりした香りで気分転換 ジャスミン茶 緊張緩和・集中力アップ 午前〜午後 勉強や仕事中にもおすすめ ルイボスティー...

暮らしになじむコンポスト|省スペース・手軽に始める生ごみリサイクル
サステナブルな暮らしに興味はあるけれど、まず何から始めたらいいか分からない……そんな方におすすめなのが、家庭でできるコンポスト。生ごみを資源に変えることで、ゴミの量を減らし、環境負荷を軽くすることができます。自治体によっては、すでに生ゴミの回収方法が別なっているところもありますよね?今回は、現代のライフスタイルに合う「匂わない・虫がわかない・省スペース」なコンポストを検索してみました。 家庭用コンポストで「匂わない」「虫が発生しない」「省スペース」「持続可能」「手軽さ」が揃うものを探すのはなかなかチャレンジですが、可能かどうか、そのためにどんな方式・工夫が必要か、現状あるものの長所&短所を整理してみましょう。 家庭用コンポストの方式と特徴 まず、方式ごとに何が得意・苦手かを把握するのが大事です。以下が主なタイプ: 方式 長所 短所 乾燥式/熱風乾燥式 水分を飛ばすので腐敗しにくく、匂い・虫発生が抑えられる。短期間で体積が減る。室内に置けるコンパクトなものもあり。 電気を使うものが多い →コストや設置場所に制約。乾燥時・排気時の臭いがわずか出ることがある。処理できる量・タイプの生ごみに制限。初期投資が高めのものも。 バイオ式/微生物式/密閉式発酵 電源不要のものもあり。微生物で有機物を分解するので自然。密閉容器だと匂いや虫を抑えやすい。 分解に時間がかかるものが多い。湿度・空気のバランスを保たないと嫌気性発酵して悪臭が出たり虫が湧いたりする。室内だと湿度・温度管理がやや難しい。専用の基材・発酵促進剤などの補助が必要になることがある。 撹拌式・回転式 空気をよく通すことで分解が早くなり、虫・匂いの抑制に役立つ。混ぜやすく管理がしやすい。 構造が少し複雑 →コストが上がる。手間がかかる(撹拌=時々攪拌する必要あり)。場所を取るものも。電動のものだと消費電力・故障リスクも。 バッグ型・布製・簡易容器型 軽くて省スペース。移動が簡単。基材交換がしやすい。コストが比較的低め。 匂い・虫対策は中身を覆う/通気性・乾燥度合いの管理が難しい。長時間放置だと手入れが必要。耐久性・密閉性で劣るものが多い。 匂い・虫を抑えるためのポイント(運用/設計) これらをきちんとできていないと、どんな方式でも「匂い/虫」が出るそうです💦おさえるためのコツ: 1.水分管理湿り過ぎると嫌気発酵が起きやすく、腐敗臭・虫発生の原因に。手で握って軽く形が保てるくらい、湿り気を少し抑えめに。乾いた新聞紙・おがくず・もみ殻などを混ぜて調節。 2.空気の供給/通気性好気性微生物が働くように空気が入る設計 or 定期的にかき混ぜること。攪拌式や回転式がこれに有利。フタの密閉と通気のバランスも大事。 3.生ごみの投入の仕方肉・魚・脂の多いものは匂い・虫を強力に呼び込みやすいため控える。細かく切る/できるだけ新しいものを投入する。投入後はしっかり覆土・覆材(あるいは乾いた素材で覆う)する。 4.温度管理熱が少しあると分解が早く、虫の発生抑制に有効。ただし高すぎても臭いや病気の原因になることも。できれば40〜60℃程度の温度が理想という意見。密閉性・フィルター・防虫構造フタがしっかり閉まること、虫が入り込む隙間がないこと、排気・通気口には防虫ネットやフィルターを付けるもの。密閉式の良いモデルだとこのあたりが工夫されている。 5.基材・発酵促進剤発酵促進剤(EM菌など)、もみ殻くん炭、炭素素材をうまく使って悪臭の元を抑える。抑臭剤や木酢液などの自然素材も効果の報告あり。...
暮らしになじむコンポスト|省スペース・手軽に始める生ごみリサイクル
サステナブルな暮らしに興味はあるけれど、まず何から始めたらいいか分からない……そんな方におすすめなのが、家庭でできるコンポスト。生ごみを資源に変えることで、ゴミの量を減らし、環境負荷を軽くすることができます。自治体によっては、すでに生ゴミの回収方法が別なっているところもありますよね?今回は、現代のライフスタイルに合う「匂わない・虫がわかない・省スペース」なコンポストを検索してみました。 家庭用コンポストで「匂わない」「虫が発生しない」「省スペース」「持続可能」「手軽さ」が揃うものを探すのはなかなかチャレンジですが、可能かどうか、そのためにどんな方式・工夫が必要か、現状あるものの長所&短所を整理してみましょう。 家庭用コンポストの方式と特徴 まず、方式ごとに何が得意・苦手かを把握するのが大事です。以下が主なタイプ: 方式 長所 短所 乾燥式/熱風乾燥式 水分を飛ばすので腐敗しにくく、匂い・虫発生が抑えられる。短期間で体積が減る。室内に置けるコンパクトなものもあり。 電気を使うものが多い →コストや設置場所に制約。乾燥時・排気時の臭いがわずか出ることがある。処理できる量・タイプの生ごみに制限。初期投資が高めのものも。 バイオ式/微生物式/密閉式発酵 電源不要のものもあり。微生物で有機物を分解するので自然。密閉容器だと匂いや虫を抑えやすい。 分解に時間がかかるものが多い。湿度・空気のバランスを保たないと嫌気性発酵して悪臭が出たり虫が湧いたりする。室内だと湿度・温度管理がやや難しい。専用の基材・発酵促進剤などの補助が必要になることがある。 撹拌式・回転式 空気をよく通すことで分解が早くなり、虫・匂いの抑制に役立つ。混ぜやすく管理がしやすい。 構造が少し複雑 →コストが上がる。手間がかかる(撹拌=時々攪拌する必要あり)。場所を取るものも。電動のものだと消費電力・故障リスクも。 バッグ型・布製・簡易容器型 軽くて省スペース。移動が簡単。基材交換がしやすい。コストが比較的低め。 匂い・虫対策は中身を覆う/通気性・乾燥度合いの管理が難しい。長時間放置だと手入れが必要。耐久性・密閉性で劣るものが多い。 匂い・虫を抑えるためのポイント(運用/設計) これらをきちんとできていないと、どんな方式でも「匂い/虫」が出るそうです💦おさえるためのコツ: 1.水分管理湿り過ぎると嫌気発酵が起きやすく、腐敗臭・虫発生の原因に。手で握って軽く形が保てるくらい、湿り気を少し抑えめに。乾いた新聞紙・おがくず・もみ殻などを混ぜて調節。 2.空気の供給/通気性好気性微生物が働くように空気が入る設計 or 定期的にかき混ぜること。攪拌式や回転式がこれに有利。フタの密閉と通気のバランスも大事。 3.生ごみの投入の仕方肉・魚・脂の多いものは匂い・虫を強力に呼び込みやすいため控える。細かく切る/できるだけ新しいものを投入する。投入後はしっかり覆土・覆材(あるいは乾いた素材で覆う)する。 4.温度管理熱が少しあると分解が早く、虫の発生抑制に有効。ただし高すぎても臭いや病気の原因になることも。できれば40〜60℃程度の温度が理想という意見。密閉性・フィルター・防虫構造フタがしっかり閉まること、虫が入り込む隙間がないこと、排気・通気口には防虫ネットやフィルターを付けるもの。密閉式の良いモデルだとこのあたりが工夫されている。 5.基材・発酵促進剤発酵促進剤(EM菌など)、もみ殻くん炭、炭素素材をうまく使って悪臭の元を抑える。抑臭剤や木酢液などの自然素材も効果の報告あり。...

健康茶のおいしさを損なわない水筒の選び方
健康やリフレッシュのために、日常的に楽しむ方が増えている「健康茶」。せっかくなら外出先でも香りや味わいをそのまま楽しみたいですよね。そこで大切なのが「どんな水筒を選ぶか」というポイントです。 今回は、健康茶をおいしいまま持ち歩くための水筒の選び方と、楽しみ方の工夫をご紹介します。 水筒で気をつけたいのは「酸化」と「におい移り」 水筒は保温性や密閉性に優れているため、持ち歩きにはとても便利です。ただし、健康茶を長時間入れて持ち歩く際に注意したいのが「酸化」。酸化が進むと、せっかくの爽やかな香りやすっきりとした味わいが損なわれ、渋みやえぐみが出やすくなります。 また、ステンレス製の水筒では、金属のにおいが移ることで風味に影響が出ることもあります。そうした心配を減らすためにおすすめなのが「内側がセラミック加工された水筒」。金属臭が発生しにくく、健康茶の自然な香りと味を長時間キープしてくれます。 おいしく飲むための工夫 2つ 健康茶を水筒で持ち歩くときにおすすめしたい工夫は次の2つです。 1.水出しで持ち歩く 健康茶を水出しにすれば、温度が低いため酸化が進みにくく、味や香りの変化を遅らせることができます。特に夏場やリフレッシュしたいときにぴったり。氷で急冷して持ち歩く場合は、少し濃いめに淹れておくと、氷で薄まってもおいしく楽しめます。 👉 Pure Ethica のブレンド茶は、水出しでもしっかり香りが立つのが特徴。ハーブや茶葉の持つ自然な甘みを、すっきり爽やかに味わえます。 2.お湯と茶葉を分けて持ち歩く 「やっぱり温かい健康茶を飲みたい」という方におすすめなのがこの方法。水筒には熱々のお湯だけを入れておき、飲む直前にティーバッグをカップに入れて淹れるスタイルです。これなら酸化を抑えられ、できたてのおいしさを味わえます。 👉 Pure Ethica の健康茶はティーバッグタイプなので、外出先でも簡単に淹れたてを楽しめます。忙しい日常やオフィスでも、ほっと一息つける時間をつくれますよ。 まとめ 健康茶は、体にやさしいだけでなく香りや味わいも多彩。だからこそ、水筒選びや持ち歩き方ひとつで、外出先でもぐっとおいしく楽しめます。 ポイントは ・酸化を防ぐ工夫をする ・セラミック加工の水筒を選ぶ ・水出しや直前抽出を試す Pure Ethica の健康茶は、水出しでもホットでも風味が豊かで、外出先でもリラックスタイムを届けてくれます。お気に入りの水筒と一緒に、毎日の暮らしに寄り添う健康茶習慣をはじめてみませんか?
健康茶のおいしさを損なわない水筒の選び方
健康やリフレッシュのために、日常的に楽しむ方が増えている「健康茶」。せっかくなら外出先でも香りや味わいをそのまま楽しみたいですよね。そこで大切なのが「どんな水筒を選ぶか」というポイントです。 今回は、健康茶をおいしいまま持ち歩くための水筒の選び方と、楽しみ方の工夫をご紹介します。 水筒で気をつけたいのは「酸化」と「におい移り」 水筒は保温性や密閉性に優れているため、持ち歩きにはとても便利です。ただし、健康茶を長時間入れて持ち歩く際に注意したいのが「酸化」。酸化が進むと、せっかくの爽やかな香りやすっきりとした味わいが損なわれ、渋みやえぐみが出やすくなります。 また、ステンレス製の水筒では、金属のにおいが移ることで風味に影響が出ることもあります。そうした心配を減らすためにおすすめなのが「内側がセラミック加工された水筒」。金属臭が発生しにくく、健康茶の自然な香りと味を長時間キープしてくれます。 おいしく飲むための工夫 2つ 健康茶を水筒で持ち歩くときにおすすめしたい工夫は次の2つです。 1.水出しで持ち歩く 健康茶を水出しにすれば、温度が低いため酸化が進みにくく、味や香りの変化を遅らせることができます。特に夏場やリフレッシュしたいときにぴったり。氷で急冷して持ち歩く場合は、少し濃いめに淹れておくと、氷で薄まってもおいしく楽しめます。 👉 Pure Ethica のブレンド茶は、水出しでもしっかり香りが立つのが特徴。ハーブや茶葉の持つ自然な甘みを、すっきり爽やかに味わえます。 2.お湯と茶葉を分けて持ち歩く 「やっぱり温かい健康茶を飲みたい」という方におすすめなのがこの方法。水筒には熱々のお湯だけを入れておき、飲む直前にティーバッグをカップに入れて淹れるスタイルです。これなら酸化を抑えられ、できたてのおいしさを味わえます。 👉 Pure Ethica の健康茶はティーバッグタイプなので、外出先でも簡単に淹れたてを楽しめます。忙しい日常やオフィスでも、ほっと一息つける時間をつくれますよ。 まとめ 健康茶は、体にやさしいだけでなく香りや味わいも多彩。だからこそ、水筒選びや持ち歩き方ひとつで、外出先でもぐっとおいしく楽しめます。 ポイントは ・酸化を防ぐ工夫をする ・セラミック加工の水筒を選ぶ ・水出しや直前抽出を試す Pure Ethica の健康茶は、水出しでもホットでも風味が豊かで、外出先でもリラックスタイムを届けてくれます。お気に入りの水筒と一緒に、毎日の暮らしに寄り添う健康茶習慣をはじめてみませんか?

無理なく続ける、わたしらしいエシカル消費
Z世代を中心に広がりつつある“エシカル消費”。環境への配慮や、人や社会にやさしい選択を意識するライフスタイルは、今や特別なものではなく、日々の暮らしに寄り添うものとなりつつあります。 けれど、完璧を求めすぎてしまうと、かえって息苦しさを感じてしまうことも。だからこそ今、自分にとって心地よく、無理のないエシカルな選択が求められているのかもしれません。 1. 「買うもの」を選ぶときの小さな意識 エシカル消費は、大きなことをしなくても構いません。たとえば、日々の買い物をほんの少し見直すだけでも、その積み重ねは未来へとつながります。 ・必要なものを、必要な分だけ選ぶ ・できるだけ長く使えるものを選ぶ ・作り手の想いに耳を傾けてみる たとえば、「Pure Ethica」のお茶は、環境や栽培方法にも配慮した自然由来の素材を使用しています。ほっと一息つく時間に、心と体にやさしい選択をしてみるのも、エシカル消費のひとつのかたちです。 2. 食べることを通して、未来に寄り添う 日々の食卓も、エシカルな視点を取り入れやすい場面のひとつです。 ・食材を無駄にしない(冷凍やリメイクを活用) ・地元の食材や旬の野菜を取り入れる ・食べることで社会課題の解決に貢献する商品を選ぶ 忙しい日々に便利でありながら、環境にもやさしい。そんな両立を叶えるのが、「SOUPe」の冷凍スープ。食品ロスになりかけた国産野菜を使い、素材のやさしさをそのまま味わえるポタージュは、体にもうれしく、心にやさしい選択肢です。 忙しい日の朝食や、お昼の軽食に。温めるだけで、手軽に“思いやりのある一品”が食卓に加わります。 3. 自分を責めない、やさしいエシカルを 「これは環境に悪いのでは?」「もっと良い選択があったかもしれない」と悩み始めると、エシカル消費が義務のように感じてしまうこともあります。でも、大切なのは自分が気持ちよく、長く続けられること。 一日ひとつ、自分にできる選択をしてみる。そんな“ほどよいエシカル”が、毎日の心を穏やかに整えてくれます。 4. 正しさより、心地よさを エシカルな暮らしは、「あれをしてはいけない」「これをしなければならない」というルールではなく、自分自身と丁寧に向き合う選択の積み重ねです。 たとえば今日、飲むお茶を選ぶとき。温めるスープを選ぶとき。その小さな選択に、ちょっとしたやさしさを添えてみませんか。 完璧でなくていい。わたしにとって心地よいエシカルこそ、きっと長く続けられるはずです。
無理なく続ける、わたしらしいエシカル消費
Z世代を中心に広がりつつある“エシカル消費”。環境への配慮や、人や社会にやさしい選択を意識するライフスタイルは、今や特別なものではなく、日々の暮らしに寄り添うものとなりつつあります。 けれど、完璧を求めすぎてしまうと、かえって息苦しさを感じてしまうことも。だからこそ今、自分にとって心地よく、無理のないエシカルな選択が求められているのかもしれません。 1. 「買うもの」を選ぶときの小さな意識 エシカル消費は、大きなことをしなくても構いません。たとえば、日々の買い物をほんの少し見直すだけでも、その積み重ねは未来へとつながります。 ・必要なものを、必要な分だけ選ぶ ・できるだけ長く使えるものを選ぶ ・作り手の想いに耳を傾けてみる たとえば、「Pure Ethica」のお茶は、環境や栽培方法にも配慮した自然由来の素材を使用しています。ほっと一息つく時間に、心と体にやさしい選択をしてみるのも、エシカル消費のひとつのかたちです。 2. 食べることを通して、未来に寄り添う 日々の食卓も、エシカルな視点を取り入れやすい場面のひとつです。 ・食材を無駄にしない(冷凍やリメイクを活用) ・地元の食材や旬の野菜を取り入れる ・食べることで社会課題の解決に貢献する商品を選ぶ 忙しい日々に便利でありながら、環境にもやさしい。そんな両立を叶えるのが、「SOUPe」の冷凍スープ。食品ロスになりかけた国産野菜を使い、素材のやさしさをそのまま味わえるポタージュは、体にもうれしく、心にやさしい選択肢です。 忙しい日の朝食や、お昼の軽食に。温めるだけで、手軽に“思いやりのある一品”が食卓に加わります。 3. 自分を責めない、やさしいエシカルを 「これは環境に悪いのでは?」「もっと良い選択があったかもしれない」と悩み始めると、エシカル消費が義務のように感じてしまうこともあります。でも、大切なのは自分が気持ちよく、長く続けられること。 一日ひとつ、自分にできる選択をしてみる。そんな“ほどよいエシカル”が、毎日の心を穏やかに整えてくれます。 4. 正しさより、心地よさを エシカルな暮らしは、「あれをしてはいけない」「これをしなければならない」というルールではなく、自分自身と丁寧に向き合う選択の積み重ねです。 たとえば今日、飲むお茶を選ぶとき。温めるスープを選ぶとき。その小さな選択に、ちょっとしたやさしさを添えてみませんか。 完璧でなくていい。わたしにとって心地よいエシカルこそ、きっと長く続けられるはずです。
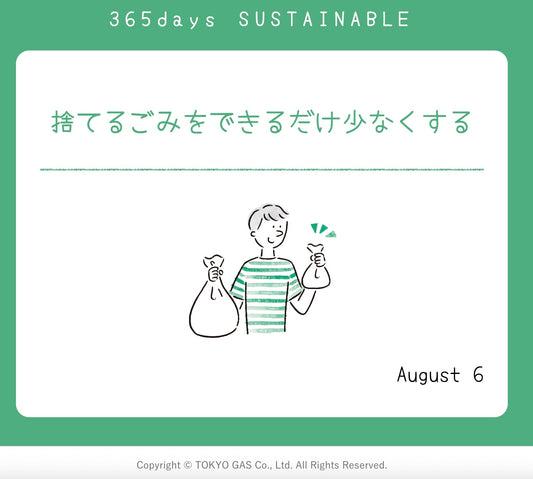
毎日1つ、サステナブルな気づきをくれる「365days SUSTAINABLE」
東京ガスが配信している日めくりカレンダー 「365days SUSTAINABLE」 は、毎日1項目、サステナブルやエシカルな暮らしのヒントを届けてくれるもの。そこに並ぶのは、「そんなの当たり前じゃない?」と思うような身近なことから、「そんな視点があったんだ!」とハッとさせられる提案まで、幅広い内容です。 便利さに慣れてしまった今の暮らしでは、つい忘れがちな感覚や、昔から受け継がれてきた丁寧な習慣。そのカレンダーは、そんな大事なことをそっと思い出させてくれるページばかりです。 我が家の日常、ちょっと昭和寄り? 私は自然光で過ごすのが好きなので、日中はほとんど電気をつけません。エアコンもあまり得意ではなく、できる限り扇風機と自然の風で過ごす派。家族には「昭和か!」と突っ込まれそうな日常です。 とはいえ、子どもがテレビを見たり、本を読んだりする時や、座っていて汗がにじむほど暑い時は、さすがに家電の力を借ります。無理せず、でもできる範囲でエコを心がける。これが我が家のスタイルです。 食材の買い方も工夫 皆さんは食材の買い物、どのくらいの頻度でしていますか?会社員時代の私は、仕事帰りにほぼ毎日スーパーに寄っていました。でも、郊外で小さな子どもと暮らす今はそうもいかず、1週間分をまとめ買い。自転車いっぱいに積み込んだり、宅配を利用したりしています。 週明けは、パズルのように冷蔵庫へ食材を詰め込み、週末には野菜をきれいに使い切ってリセット。食品ロスを減らすためにも、食べきれない量は買わないように心がけています。 小さな習慣から始める食品ロス削減 家庭から出る食品ロスも、実は全体の大きな割合を占めています。だからこそ、「買いすぎない」「食べきる」を意識することが大事。 私の場合は、 ⚪︎食べきれないリスクを極力ゼロに ⚪︎捨てるゴミをできるだけ減らす ⚪︎生ゴミは自然乾燥してから捨てる(今後はコンポストを始めたい) これらをゆるく続けています。 カレンダーをめくるたび、「そうそう、これ大事だよね」と気づくことがあります。サステナブルって、特別なことをするよりも、日々の小さな選択や習慣から始まるのかもしれません。 引用(東京ガス365days SUSTAINABLE)https://www.toshiken.com/sustainable/
毎日1つ、サステナブルな気づきをくれる「365days SUSTAINABLE」
東京ガスが配信している日めくりカレンダー 「365days SUSTAINABLE」 は、毎日1項目、サステナブルやエシカルな暮らしのヒントを届けてくれるもの。そこに並ぶのは、「そんなの当たり前じゃない?」と思うような身近なことから、「そんな視点があったんだ!」とハッとさせられる提案まで、幅広い内容です。 便利さに慣れてしまった今の暮らしでは、つい忘れがちな感覚や、昔から受け継がれてきた丁寧な習慣。そのカレンダーは、そんな大事なことをそっと思い出させてくれるページばかりです。 我が家の日常、ちょっと昭和寄り? 私は自然光で過ごすのが好きなので、日中はほとんど電気をつけません。エアコンもあまり得意ではなく、できる限り扇風機と自然の風で過ごす派。家族には「昭和か!」と突っ込まれそうな日常です。 とはいえ、子どもがテレビを見たり、本を読んだりする時や、座っていて汗がにじむほど暑い時は、さすがに家電の力を借ります。無理せず、でもできる範囲でエコを心がける。これが我が家のスタイルです。 食材の買い方も工夫 皆さんは食材の買い物、どのくらいの頻度でしていますか?会社員時代の私は、仕事帰りにほぼ毎日スーパーに寄っていました。でも、郊外で小さな子どもと暮らす今はそうもいかず、1週間分をまとめ買い。自転車いっぱいに積み込んだり、宅配を利用したりしています。 週明けは、パズルのように冷蔵庫へ食材を詰め込み、週末には野菜をきれいに使い切ってリセット。食品ロスを減らすためにも、食べきれない量は買わないように心がけています。 小さな習慣から始める食品ロス削減 家庭から出る食品ロスも、実は全体の大きな割合を占めています。だからこそ、「買いすぎない」「食べきる」を意識することが大事。 私の場合は、 ⚪︎食べきれないリスクを極力ゼロに ⚪︎捨てるゴミをできるだけ減らす ⚪︎生ゴミは自然乾燥してから捨てる(今後はコンポストを始めたい) これらをゆるく続けています。 カレンダーをめくるたび、「そうそう、これ大事だよね」と気づくことがあります。サステナブルって、特別なことをするよりも、日々の小さな選択や習慣から始まるのかもしれません。 引用(東京ガス365days SUSTAINABLE)https://www.toshiken.com/sustainable/